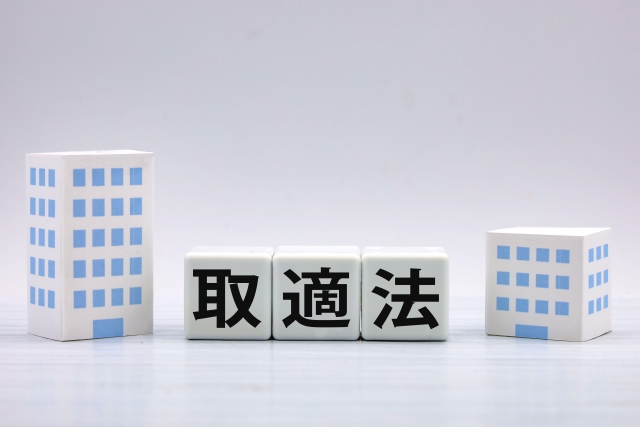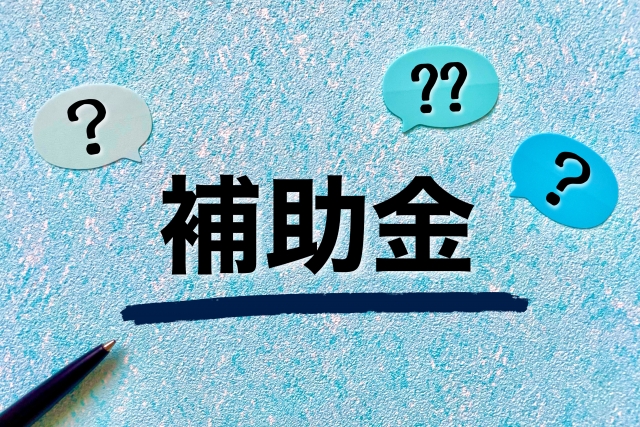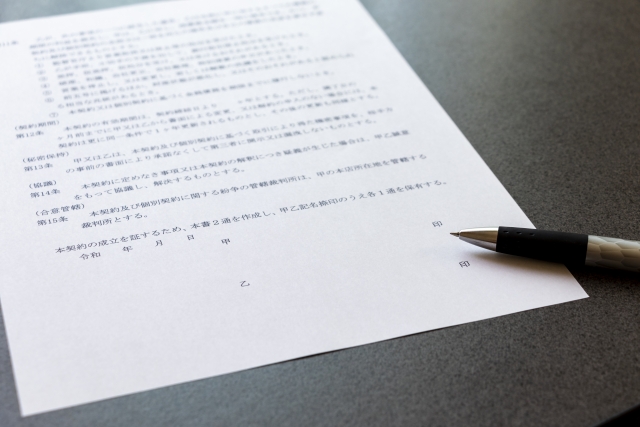労働者の競業避止合意の有効性と人手不足対応
- 2025/5/1
- 診断士の視点

弁護士・中小企業診断士 伊藤 諭
はじめに
2010年代以降、景気の回復に伴って企業の人手不足感が増しています。企業の雇用人員判断D.I.(雇用が「過剰である」と回答した企業の割合から、「不足している」と回答した企業の割合を引いたもの。)は2010年以降一貫してマイナスとなっており、コロナ禍を経てその傾向は増していると言えるでしょう。令和6年版労働経済白書(労働経済の分析)では、「人手不足への対応」を副題として、誌面の半分を割いて分析しています。令和6年版労働経済の分析〔令和6年9月6日閣議配布〕

図1:雇用人員判断D.I.の推移(厚生労働省令和6年版労働経済の分析 p96より引用)
そんな中、人材の囲い込み又は競業他社への人材や情報流出を防止するため、従業員との間で競業避止合意をする企業が多くなっています。今回、その効力を裁判例とともに振り返りつつ、組織論的な観点からの考察も加えてみたいと思います。
1.労働者の競業避止義務とは

労働者の競業避止義務とは、労働者が使用者と競合する企業に就職したり自ら開業したりしないようにする義務をいいます。労働者の競業避止義務については、法律上、明文の規制はありません(取締役等については、明文の規制があります。会社法356条ほか。)。もっとも、労働契約の存続中は、就業規則や労働契約上の特約がなかったとしても、信義則上、競業避止義務を負うと考えられています。これに対し、労働契約の終了後については、何らか特別の合意がない限り、労働契約を根拠とする信義則上の競業避止義務は消滅することになります。使用者は、労働者が退職後、競合他社に移籍したり競合として独立することにより、ライバルが増えるのみならず、自社の経営上のノウハウや顧客の流出などにより、競争力が低下することを懸念します。これらを回避するため、労働者の退職後も、一定の範囲で競業避止義務を課す合意(競業避止合意)をしようとすることがしばしば行われています。 競業避止合意のタイミングとしては、①入社時に同意書(誓約書)を作成する方法、②昇進時に作成する方法、③退職時に作成する方法が考えられます。タイミングが後になるほど、退職後の違反行為と時間的に近接することになるので有効性が高まる反面、作成のインセンティブが少なくなり協力が得られないこともあり得ます。
2.競業避止合意の有効性
競業避止合意は、使用者の営業の利益を守ろうとするものである反面、退職労働者にとっては職業選択の自由(憲法22条)を制限される上、競争制限により独占集中を招き一般消費者にとっても不利益があるという側面もあるため、合理的範囲を超えて過度に制限すると、公序良俗に違反し無効であると評価されるおそれがあります。
(1)判断基準
競合避止合意の有効性(公序良俗に違反しないかどうか)の判断基準について、裁判例を元に分析すると、概ね次のような判断項目で、①これにより守られるべき使用者の利益、②これによって生じる労働者の不利益、③社会的利害を考慮しています。

(2)裁判例

近時、競業避止合意の有効性が争いになった事案を紹介します。
- ア REI事件判決(東京地裁令和4年5月13日判決)
システムエンジニア派遣会社が、退職後、転職先から同じ派遣先の仕事に従事した退職労働者に対して約定の損害金(3か月分給料相当分)の請求をした事件。退職労働者は退職時に「秘密保持契約書」を作成しており、同書面には退職後1年間は取引先に就職しないこと等を誓約し、誓約に違反したときは最後の3か月分相当額の賠償金を支払うこととする条項があった。 裁判所は、競業避止合意自体の存在は認めつつ、そもそも本件競業避止合意で守るべき独自のノウハウなどがあったとは言えず 、転職先の職種、地域、範囲の限定もなく、代償措置(退職金、手当てなど)も取られていないことから、期間が1年にとどまることを考慮しても競業避止合意は公序良俗に反し無効と判断した。 - イ 日本産業パートナーズ事件判決(東京高裁令和5年11月30日判決)
投資事業有限責任組合財産の運用等を行う会社を退職した従業員が、退職金の一部を不支給とされたことを不服として、会社に対して退職金の請求をした事件。この従業員は、転職活動中に、会社で関与した案件に関する資料や面談記録などを大量に印刷して持ち出した上で、競合他社である転職先においても同一投資先の案件に関与していた。なお、入社時に競業避止合意の誓約書は提出していたが、退職時には誓約書の作成を拒絶していた。同社の退職金規程には、一定の場合に退職金の全部又は一部不支給条項があった。 - ウ 分析
結論が異なる2つの事案を取り上げました。
REI事件においては、高度な秘密やノウハウを持つわけでもない一般の従業員も含めた労働者に対して広く競業避止合意を締結していたことが伺われます。裁判所においては、退職労働者の職業選択の自由を制限してまで守ろうとするべき企業の利益の存在を立証できなかった時点で結論は厳しいものとならざるを得ませんでした。他方、日本産業パートナーズ事件については、この従業員の行為の悪質性が結論に大きく影響しているものと思われます。単なる競合への転職のみならず、不正競争防止法違反にもなり得る程度の情報の流出が認められたため、「入社時の競業避止合意」という時系列的には遠い合意の有効性を認めてでも会社を勝たせる必要性があったものと推測します。退職時には誓約書の作成を拒絶しているわけですから、入社時の誓約書がなければ退職後の競業避止合意が存在しないこととなり、同じ結論になっていたかは分かりません。このとおり、競業避止合意は、裁判所が勝たせたいと考えたときに使えるようなものであって初めて意味を持つものと言えます。
(3)意味のある競業避止合意をするために
裁判所の発想を踏まえて、競業避止合意を行うに当たっては、いざというときに役に立つものでなければなりません。そのために必要な観点を以下にまとめます。
ア 守るべき会社の利益を明確にする
REI事件では、守るべき会社の利益が判然としていませんでした。「ノウハウの流出」「企業秘密の保護」といった抽象的なものではなく、具体的に他社からも理解される利益の保護の必要性がなければなりません。これがない(おそらく多くの会社がそうであると考えられます)場合は、競業避止合意の効力について割り切って考えることも1つの判断です。
イ 守るべき利益に応じて、対象者と禁止行為を明確にする
アで守るべき利益が明確になった場合、競業避止合意の対象者やその禁止行為も自ずと限定されるはずです。守るべき利益との関係で、必然性のない全社員を対象にしたり、不合理に禁止行為の範囲を拡大してしまうと、合意の効力が無効となるおそれがあります。
ウ 明示的に代償措置を講じる
裁判所は、会社側の競業避止の必要性だけではなく、退職労働者の職業選択の自由の制限という不利益についても重要な判断要素としています。イで限定した対象者に対して、「競業避止合意の対価」であることを明示した代償金の支払いを行うと有効性が高まります。もし、代償金を払う価値がないと考えるのであれば、それだけアで検討した利益の価値が高くないということですので、やはり効力については割り切って考えていただく必要があります。
3.競業避止合意の組織論的観点からの考察
最後に、競業避止合意の組織論的な意味とその対応策についての考察を加えて結びといたします。
(1)企業側の事情
競業避止合意をしたい会社側の事情としては、概ね次のようなが考えられます。
- 人的資本流出リスク
労働者がライバル企業に行ってしまうという意味のみならず、その労働者に紐付く人間関係、取引関係など属人的な関係をライバルに移転させてしまうリスクが考えられます。
- 育成コストの回収
労働者を育成するには人的物的コストが発生します。育成が終わってようやく回収のフェーズに入った段階で、人材が他社に流出してしまうことは育成コストの回収という意味においても損失と言えます。
- 競争環境の激化
競争環境が激化すると、業界に精通した人材は奪い合いの様相を呈することになります。流出した人材の代替を確保することも大きなコストが発生します。
(2)従業員側の事情
他方、従業員側の事情としては、次のようなものが考えられます。
- 職業選択の自由
労働者として、キャリアアップを選択することは自然の発想です。自社での経験を活かして他社でよりよい処遇を受ける機会を制限されたくないという欲求は当然のものと言えます。
- 労働市場の流動化
競争環境の激化は、労働者側から見れば労働市場の流動化と捉えることができます。労働市場の流動化は、ステップアップ転職の動機となり得ます。
- 企業への不信
労働市場が流動化しても、自社の労働環境に魅力があれば転職を引き留める誘因となり得ます。転職には、大なり小なり企業への不信が存在することがむしろ通常と言えます。
(3)合理的な対応策

このように考えると、競業避止合意をすること自体は、根本的解決策でも万能な解決策でもないことがわかります。逆に、競業避止合意の効力を強めることで、他社からの人材確保が困難となり、自社の首を絞めかねないことにもつながります。人手不足の解消という意味における対応策としては、究極的には王道を行くほかなく、会社自体の魅力を向上させるということに尽きると言えるでしょう。例えば、次のような対応策が考えられます。
- エンゲージメント(会社との関係性)の強化
会社と労働者との間のコミュニケーション施策を充実し、関係性を強化していくことが必要です。
- キャリアパスの提供
自社における自分の将来に魅力を感じてもらい、人材の定着を図るため、キャリアパスの提供も重要な観点です。
- 企業文化の魅力化
労働者を惹きつける企業文化は、人材の確保、定着に直結します。この会社だからこそ夢を実現できる、と思わせるような魅力を発信していきましょう。
4.まとめ
自由競争を制約する要素は、長期的視点において自社のためにならないことが多いと言えます。このような観点で自社の人事施策を検討されることをお勧めいたします。
企業が明確な基準を持ち適切な対策を講じることで、従業員が安心して働ける職場環境を実現できればと願っています。