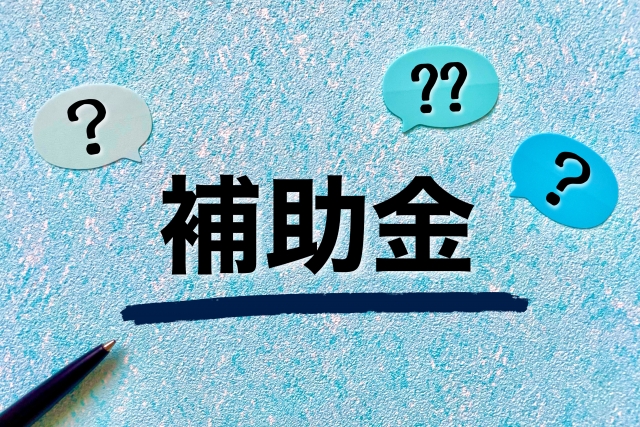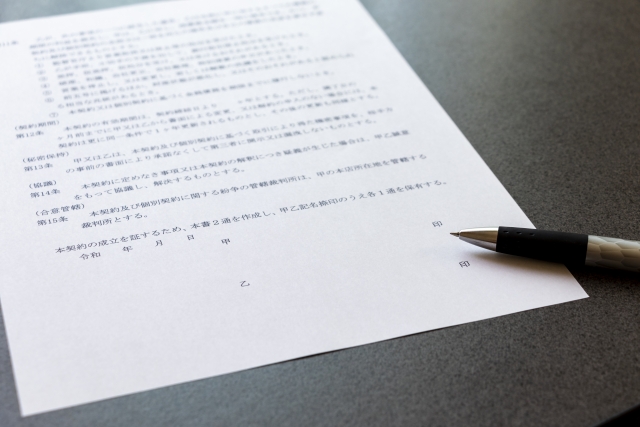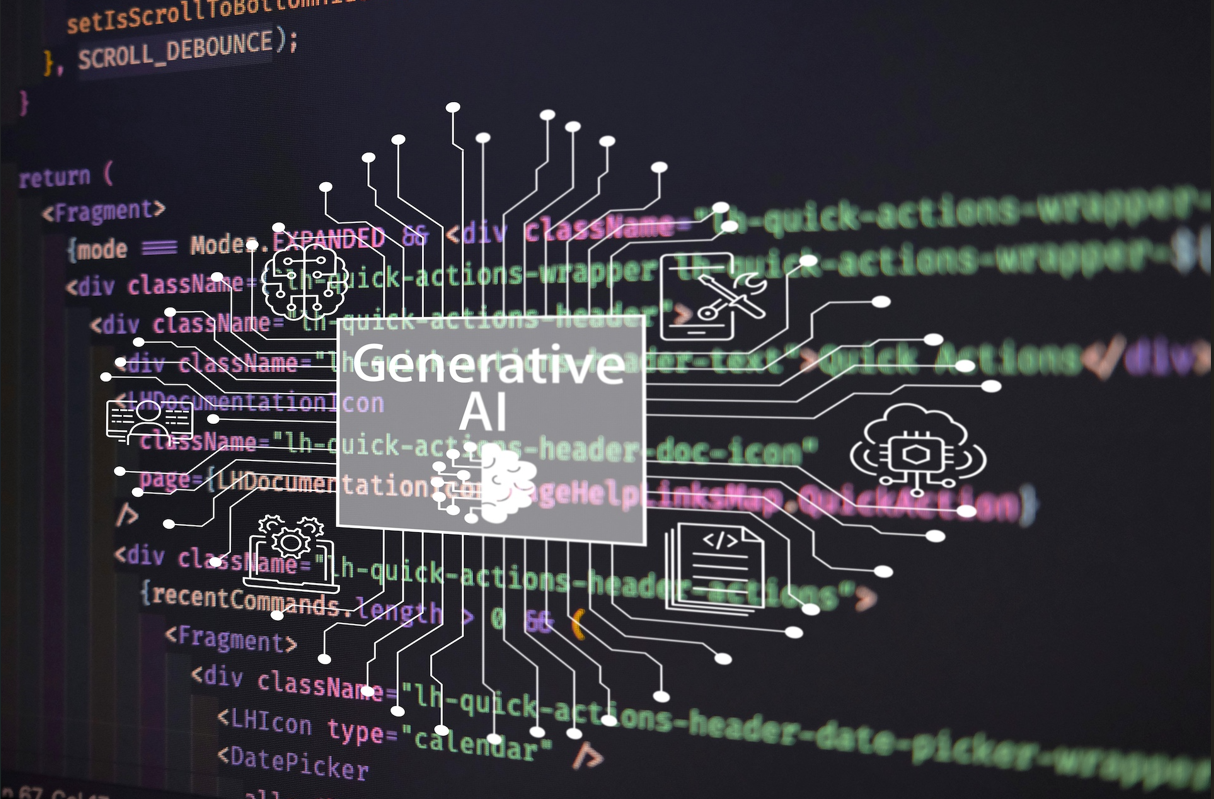職場における心理的安全性って何ですか
- 2025/7/1
- トピックス

中小企業診断士 平田 仁志
ある時、当時経営改善の支援をしていた会社を訪問したら社長が嬉しそうに言いました。「取引先の社長が、『以前に比べて明るい会社になったね、社員がみんないきいきと働いているよ。』と言ってくれました。」
暗い雰囲気だった会社を変えるために、食事会を定期的に開いたり、プロジェクトチームを作って社員参加で改善を進めようとしたり、社長がいろいろと努力してきたことが報われて、本当にうれしそうでした。
そう言えば町工場の経営改善で有名になったダイヤ精機の諏訪貴子社長は著書「町工場の娘」で、東京出身なのにわざと大阪弁で社員と話す日を作ったりして明るい会社を作ろうとした、と書いています。取引先から「ダイヤ精機はみんな楽しそうに働いているね」と言われるそうです。
どうしたら明るい会社が作れるか、明るい会社はなぜ業績が良いのか、ということについて、以下、心理的安全性という言葉から考えていこうと思います。
1.心理的安全性とはどんなものか

心理的安全性の重要性は、10 年ほど前に、あのグーグルの社内調査で、効果的なチームの最重要要素として脚光を浴びてから注目されるようになりました。
心理的安全性の高い職場では、こんなことを言ったら怒られるんじゃないかとか、目立ちたがりと思われて同僚から嫌われるんじゃないかとか考えず自由に発言できるということが基本的な条件です。
しかし現実は、会議を開いても上司が一方的に話して、誰も意見を言わないというような状況がかなり一般的ではないでしょうか。こんな発言をしたら、後から何を言われるか分からないから、会議では言えないということはよくあることではないでしょうか。
何でも話せるというのは、話したらちゃんと聞いてくれる人がいるということですね。話したことについてちゃんと受け止め、好き嫌いではなく、共通の目的に対しての良い悪いをきちんと議論できる。提案が良いとなったら、みんなでちゃんと実行する。ホンダのワイガヤと言われるような風土が、ホンダの強みだと言われています。ワイガヤというのは年齢や役職、専門分野の垣根を超えて、誰が言ったかに関係なく、自由に本音で意見をぶつけ合うことです。
2.心理的安全性だけで良いか

何でも話せる心理的安全性が確保されていればそれでよいかというと、どうでしょう。何でも話せるけど、特に明確な目的とかはなく話している、というといわゆる茶飲み話になってしまいます。リラックスして何でも話せるのは気楽でいいけど、それを職場の中で延々と続けていたら、むなしい感じになってしまい、なんのために話してるんだろう、と思うようになってしまいます。
実はホンダのワイガヤはイノベーションを起こすという目的を共有した上で、自由に議論しているのです。そこから新しいアイデアが生まれ新製品開発ができ、成果をみんなで実感できたから、組織風土として根付くほどに続いたのです。
3.組織の状態を心理的安全性と達成基準の高低の組み合わせで考える
組織の状態を心理的安全性と達成基準の高低の組み合わせで考えると下の表のようになります。

ご自分の職場はどこに近いですか。
達成基準が低く心理的安全性も低い「サムい職場」は比較的少ないかもしれません。目標もなく、職場にいる間できるだけ余分なことはしないという状態が長続きするとは思えないからです。
達成基準は低いが心理的安全性は高い「ヌルい職場」は、安定した売上が確保できていて業績の心配がない会社ではありうる状態ですね。職場のみんなが友達のような関係で居心地がいいけど、働いている気がしない、充実感のない毎日になるでしょう。
比較的多いのが「キツい職場」かもしれません。目標達成へのプレッシャーが強いばかりで、お客様の役に立つという本来の会社の目的がないがしろにされている会社もあります。
そのような会社で、昇給昇格が社長のさじ加減で行われていて、その評価基準が社員には知らされていないという場合があります。すると、社員は何をするにも社長の顔色を窺うようになってしまいます。お客様のためによいと思ったことでも、社長の気に入るかどうかを考えなければならなくなってしまうのです。心理的安全性が低い状態です。
それでも変化があまりない社会だったら、従来通りのやり方でとにかく頑張るということで何とかなることもあるかもしれません。しかし、社会の変化が激しい現在、その変化を考えず従来通りのやり方で頑張っても成果に結びつかないことが多くなっているのではないでしょうか。社長が昔やって成功したことでも、今はもう通用しない。現場の社員にはそれが分かっているけど社長が気づかないままでいる。現場の社員は下手に自分の考えを社長に伝えると何を言われるか分からないから、言えない。その結果社会の変化に遅れてしまって発展できないという会社もあるのではないでしょうか。
4.学習する職場(心理的安全性が高く達成基準が高い職場)を実現するためにどうするか
会社の目的が共有されていて、社員の心理的安全性が高く、気が付いたことは何でも言えるような職場では、意見交換が活発にでき社員が成長できます。そのような学習する職場を目指したいものです。そのためには、私の経験や、前に述べた「町工場の娘」のダイヤ精機のような会社の例を参考にして考えると以下のようなことが効果的と考えます。
①社長と社員、あるいは社員同士で気楽に話ができる機会を作る。その月に誕生日を迎える社員を集めて食事会をするのも一つの方法です。ある会社では月に一度、社員が勝手に作ったグループごとに会社のお金で食事に行くようにしていました。
②「否定されない」「意見していい」と感じられる雰囲気を醸成する。社長やリーダーには知らないことを認める姿勢を示すことや失敗から学んだ経験を話し、失敗を学びに変えられると感じてもらうようにすることが重要です。
③目的の共有。よくビジョンとか理念とかと言われますが、会社が何を目指しているかについて共有することが重要です。
④共有している目的に照らした評価基準の明確化。どんな行動が求められるか、社内の共通認識にもとづいた行動の評価基準を設け、その基準に従って社員にとって納得感のより高い人事評価をする。
⑤行動目標については、年度末にいきなり評価をするのではなく、月一回とか2カ月に一回、ワンオンワンミーティングによる進捗度確認をすることにより社員の成長を促す効果が期待できます。
以上心理的安全性の観点から、理想の職場の在り方について述べてきました。皆様の職場の改善に少しでも参考にしていただければ幸いです。