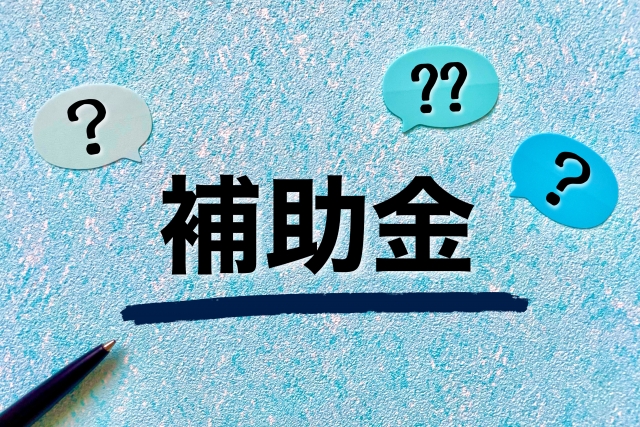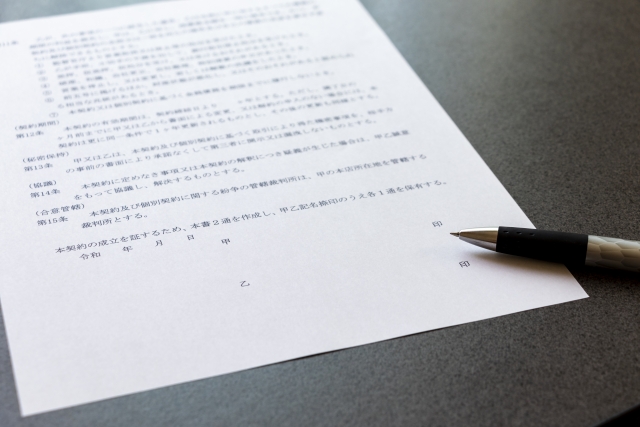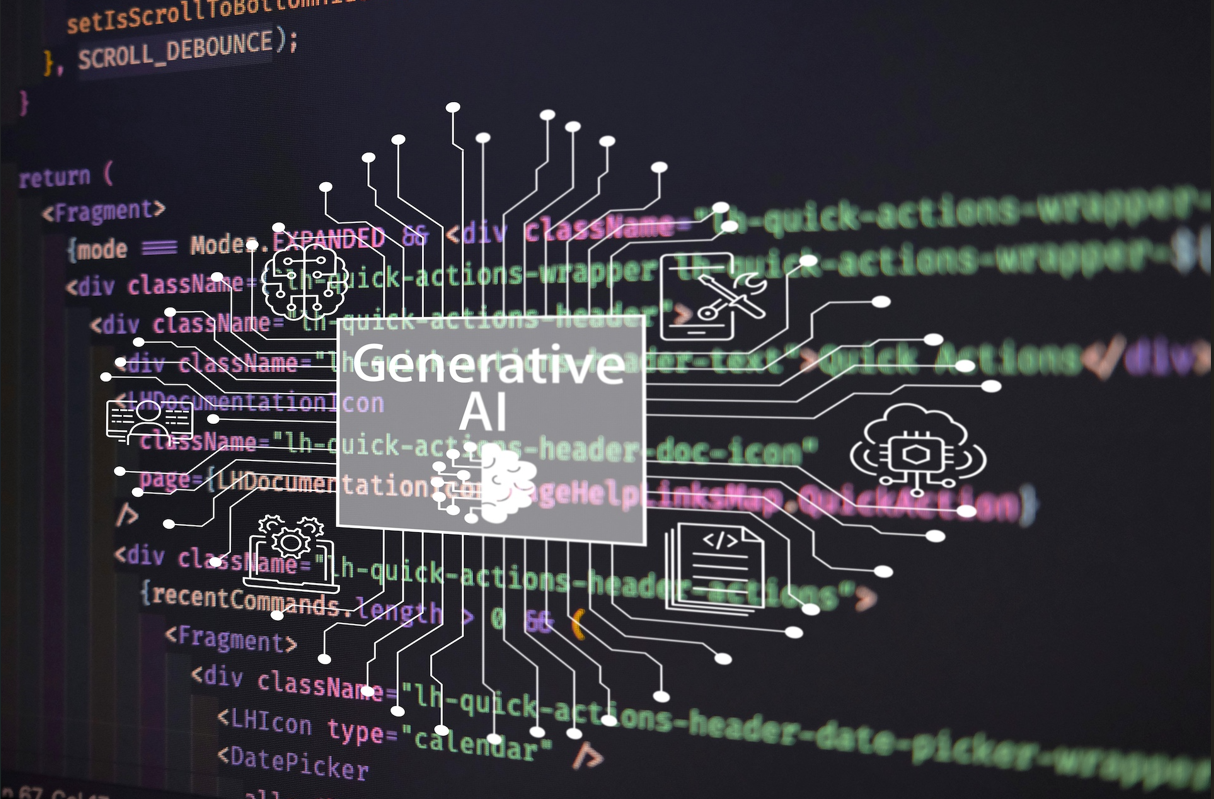中小企業の賃上げに向けた課題と、課題解決に向けた国の施策について
- 2025/9/1
- トピックス

中小企業診断士 岩水 宏至
1.2025年の賃上げ
日本労働組合総連合会(連合)がまとめた2025年春闘の最終集計1)によると、ベースアップと定期昇給を合わせた平均賃上げ率は5.25%と1991年以来の高水準な結果となりました。一方で調査結果を詳しく見たところ、従業員300人未満の企業の平均賃上げ率は4.65%でした。同調査における従業員300人以上の平均賃上げ率が5.33%であることを考慮すると、大企業と中小企業の賃金格差は広がっていると言えます。
連合は、2025年の春闘において、中小企業で6%以上の賃上げを求める方針を掲げていました。しかしその水準はおろか5%にも届きませんでした。その原因は、価格転嫁が十分に進まない会社があったことや、物価高による内需の低迷があったことによるものとしています。
2025年版中小企業白書でも「中小企業においても、正確な原価構成の把握や適切な価格交渉などを通じて価格転嫁を推進することで好循環を実現し、更なる労働生産性の向上につなげていくことが期待される」としています。中小企業にとって、価格転嫁と労働生産性の向上は賃上げに向けた課題と言えます。
2.課題解決に向けた国の施策

これらの課題を解決するための政府の施策を以下に挙げます。中小企業が持続的な賃上げを実現していくためには、これらの施策も適宜活用することによって価格転嫁を行い、合わせて労働生産性の向上を図ることが重要です。
①労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針2)
政府は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」として、発注者と受注者が取るべき行動を取りまとめています。このなかで、発注者は労務費の取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定する、受注者は労務費の転嫁が必要とする根拠資料として公表資料を用いること、発注者と受注者の双方は交渉の記録を作成し保管するといった行動指針が示されています。
中小企業庁では、指針策定直後に約900の経済産業省所管の業界団体へ周知を行ったほか、経済産業省のホームページに賃上げ率などの情報を掲示しました。さらに業界団体ごとに策定している自主行動計画への反映を要請するなど、引き続き同指針に沿った行動の徹底を産業界へ要請していく方針としています。
②賃上げ促進税制3)
賃上げ促進税制とは、従業員の賃上げや、人材育成への投資に積極的な企業が、所定の税額控除を受けられる制度です。青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除することができます。
中小企業の場合、雇用者全体の給与等支給額(国内雇用者の給与、賃金、賞与などの給与所得に該当するもの)の増加率によって、最大30%の税額控除を受けられます。また、上乗せ要件として、教育訓練費については、前年度比5%以上の増加により税額控除率を10%上乗せできます。さらに賃上げ促進税制の一環として、新たに女性活躍支援の観点から加算措置が設けられました。「くるみん認定」以上あるいは「えるぼし認定(2段階目)」以上の認定(「くるみん認定」は子育てサポート、「えるぼし認定」は女性活躍促進の取り組みが優良な企業を、厚生労働大臣が認定する制度。それぞれ認定基準によりいくつかのレベルが設けられている)を得ている場合、さらに税額控除率を5%上乗せすることができます。これら上乗せ措置の併用により税額控除率を最大45%とすることができます。また、中小企業については控除しきれなかった控除額について5年間の繰越しが可能です。
本制度は税額控除であることから高い節税効果が得られます。制度を活用して賃上げができれば、従業員満足度が向上し、離職率低下やモチベーション向上にもつながります。一方で、本税額控除は、基本的には前年と比較した給与増額率に対する単発的な控除です。控除を受けた翌年以降は国からの支援はないことを念頭におき、計画的に給与増額を実施する必要があることを考慮しなければなりません。
③中小企業省力化投資補助事業4)
本事業は「中小企業省力化投資補助金」により、省力化設備を導入するために必要な経費の一部を補助することによって、人手不足に悩む中小企業等の省力化投資を後押しするものです。製品カタログに登録された省力化製品を選ぶ「カタログ注文型」に加え、2025年からはオーダーメイド(セミオーダーメイド)で省力化設備を導入できる「一般型」が新設されました。
「カタログ注文型」の補助率は1/2以下、補助上限額は従業員数によって200万円~1,000万円と異なり、大幅賃上げにより上限額が引き上げられる特例もあります。「一般型」の補助率は中小企業が1/2、小規模・再生事業者が2/3、補助上限額は従業員数によって750万円~8,000万円と異なり、大幅賃上げ特例によって補助金上限は最大1億円となっています。
省力化製品を導入したい事業者には、費用負担の軽減が可能になります。製品導入により生産性向上と人手不足の解消が可能になるとともに、従業員がより付加価値の高い業務に取組むことも可能です。
「カタログ注文型」は、2026年9月末頃まで補助事業の申請を受け付けるとされています。一方で「一般型」は2025年8月末に既に第3回公募の申請受付が終了しています。第4回公募の実施が見込まれるものの今年度の申請を検討する場合は急ぐ必要があります。
3.まとめ
2025年8月4日に行われた厚生労働省の中央最低賃金審議会では、2025年度の最低賃金の目安を全国の加重平均で時給1,118円にするとしました。これは過去最大の増加幅です。最低賃金の引き上げは労働者が生活水準を維持するために必要な措置である一方、中小企業にとっては経営の圧迫につながることが懸念されます。
中小企業が持続的な賃上げを実現するために、価格転嫁や生産性向上は待ったなしです。上述した政府の既存の支援策だけでなく、常に最新の情報を収集し、経営力の強化を実現していくことが重要と考えます。

1) 日本労働組合総連合会「第7回(最終)回答集計(2025年7月1日集計・7月3日公表)」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/yokyu_kaito/
2) 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について(2024年2月 内閣官房・公正取引委員会
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001738653.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
3) 中小企業向け「賃上げ促進税制」(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
4) 中小企業省力化投資補助金
https://shoryokuka.smrj.go.jp