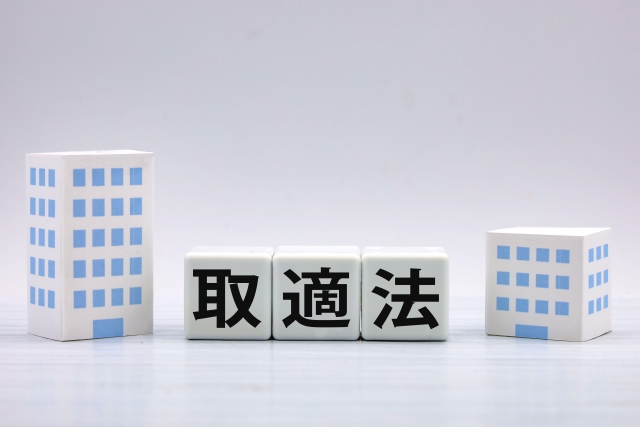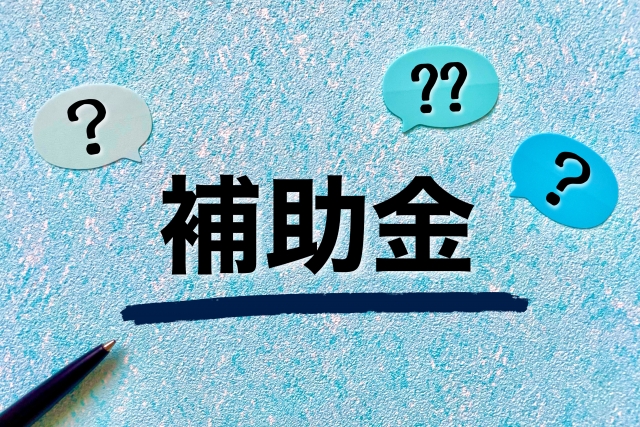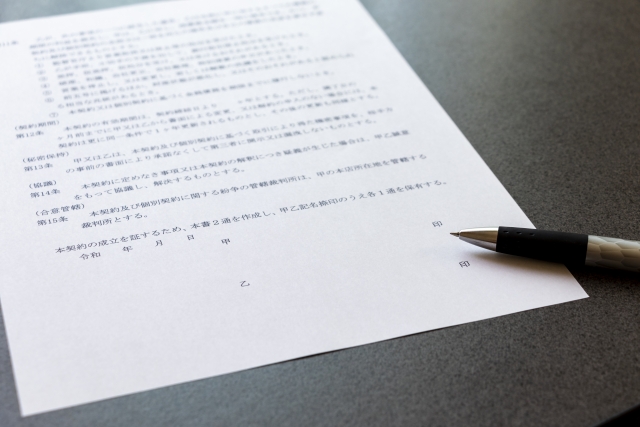中小企業診断士の視点からみた不動産
- 2025/10/1
- 診断士の視点

中小企業診断士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 田中 一朗
中小企業にとって、不動産は事業の基盤であり、資金調達の手段であり、場合によっては収益を生む資産としても機能します。一方で購入や維持に伴う借入返済・固定資産税・修繕費などが資金繰りを圧迫する場合もあります。さらに資金が不動産に固定されることで、新規投資や資金調達の自由度が下がり、環境変化に対応しづらくなるといった問題が生じる可能性があります。
このように、不動産は経営に安定をもたらす一方で、扱い方を誤ると大きな制約要因にもなり得ます。本稿では、中小企業診断士の視点から、不動産をどのように活かし、事業の成長や事業承継に結び付けていくべきかを考えていきます。
1.財務面(信用力と資金調達力の向上)
不動産の所有や購入は貸借対照表に大きな影響を与え、自己資本比率や固定比率といった財務指標に直結します。土地や建物を所有することは、企業の「安定感」として評価され、取引先や金融機関からの信用も得やすくなります。
金融機関が不動産を重視する理由は、担保としての安定性と収益の安定性にあります。不動産は価値の変動が比較的小さく、回収可能性が高い資産とみなされます。さらに、賃貸収入があれば返済原資の裏付けともなります。ただし、固定資産税や修繕費などの維持コストを考慮し、保有と賃借のどちらが適切かを検討することが重要です。
2.事業戦略面(成長と競争力を支える基盤)
不動産は企業の事業戦略と密接に結びついています。立地条件は売上、物流効率、人材確保に直接影響を与えます。
・小売業では商圏分析に基づく立地選定が収益性を大きく左右します。
・製造業では工場立地が調達や配送の効率に直結します。
・サービス業では、アクセスの良さや街の雰囲気がブランドイメージに影響します。
市場調査や需要予測を踏まえた不動産活用は、競争力を維持するうえで不可欠です。
3.リスク管理面(長期的な安定と事業継続)
不動産は長期的に活用できる資産ですが、同時に災害、法的制約、老朽化、市況変動といったリスクを抱えています。これらを事業継続計画(BCP)に組み込み、代替拠点の確保や再開発の検討を行うことが求められます。長期的なリスクマネジメントを行うことが、企業の持続的成長に直結します。

4.事業承継における不動産の留意点
事業承継では、経営者個人が所有する土地に会社が建物を建てているケース(この土地のことを「底地(そこち)」といいます。)がしばしば問題となります。この場合、会社には借地権が発生し、税務・権利関係・資金調達に影響を及ぼします。
4.1 税務面:借地権の評価は相続税に直結します。使用貸借契約(無償での貸借)であれば課税評価を抑えられますが、承継後の担保利用に制約が生じます。すでに借地権が発生している場合には「無償返還届出制度」を活用し、将来の課税関係を明確にしておくことが有効です。この辺りはトラブルになりやすく、かつ税務上の影響も相続税、法人税、所得税など多岐にわたるので資産税に強みを持つ税理士を選ぶことが重要です。
4.2 権利関係:借地に関して最も注意すべきは、契約内容の不明確さです。賃貸借契約書が存在しない、あるいは更新条件や地代改定の取り決めが曖昧なままでは、承継後に親族間で「借地権があるのか」「使用貸借なのか」といった争いが生じる可能性があります。これにより、事業の継続に支障をきたすリスクも想定されます。
・契約書の整備:借地権か使用貸借かを明文化し、存続期間・更新条件・承諾料の取り扱いを明確にしておくことが不可欠です。
・共有名義の解消:相続により底地が複数の親族で共有されると、売却や担保設定などの意思決定に全員の同意が必要となり、実務が滞ります。承継前に法人または後継者が単独所有できる形に移行するのが望ましいです。
・完全所有権の確立:借地と底地を一体化して完全所有権とすることで、資産の流動性が高まり、将来的な売却・担保提供が容易になります。これにより金融機関からの評価も高まり、資金調達が有利になります。
4.3 資金面:底地を法人が買い取る場合、まとまった資金が必要になります。特に市街地や商業地の底地は評価額が高いため、承継計画の中で十分な準備をしておくことが重要です。
・資金調達方法:金融機関からの融資を検討する場合、担保評価や返済原資の裏付けが不可欠です。借地権が整理されていないと融資が難しくなるケースもあるため、権利関係の整備と並行して資金調達計画を立てる必要があります。
・納税資金の確保:相続時には底地そのものが課税対象となり、さらに一体化により資産評価額が上がる場合もあります。相続税や贈与税の負担を見据え、生命保険の活用、延納や物納といった制度の利用も含めて資金繰りを検討することが求められます。
・出口戦略:購入後にどのように底地を活用するかをあらかじめ想定することも重要です。借地権者との合意により一体化を進め、完全所有権化することで資産価値を高めるのか、あるいは賃貸収益を安定的に得るのか、方向性を明確にしておく必要があります。
事業承継の成功には、株式や経営権の移転だけでなく、不動産の権利関係の整理と活用方針の策定が欠かせません。承継後に「土地が共有状態で意思決定ができない」「借地権の扱いが不明確で融資が受けられない」といった問題が発生すれば、後継者の経営は大きく制約を受けます。
4.さいごに
不動産は会社の経営を支える一方で、資金繰りや事業の柔軟性に影響を与える面もあります。そのため「必ず所有すべきもの」と考える必要はありません。
ただ、資金に余裕があるときには、不動産を持つという選択肢を検討してみるのも一案です。土地や建物を所有していれば、金融機関からの信用度が増すほか、事業承継のときに後継者が安心して経営を引き継げる基盤にもなります。
不動産は無理に持つものではなく、「あれば心強い資産」です。事業の状況や将来の展望に合わせて、投資の選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。