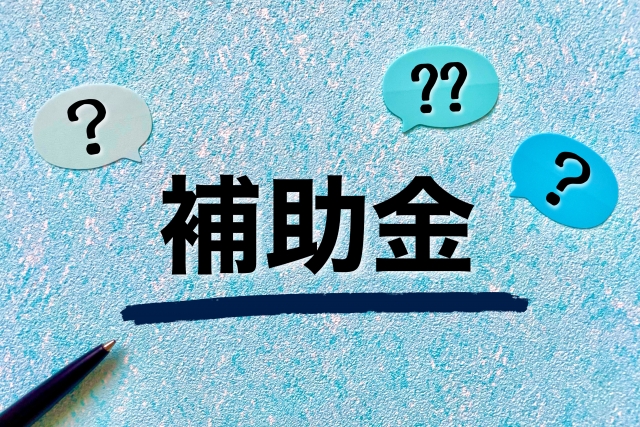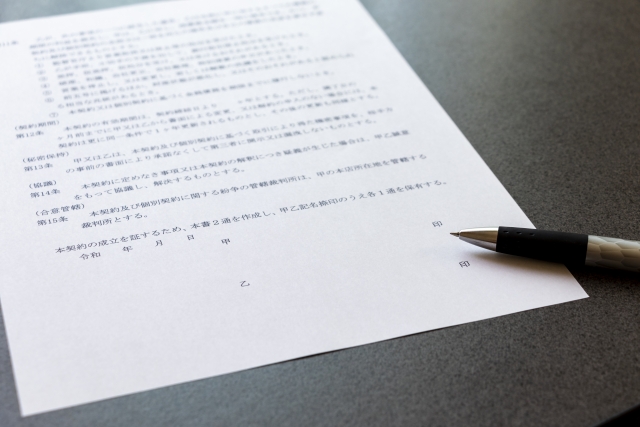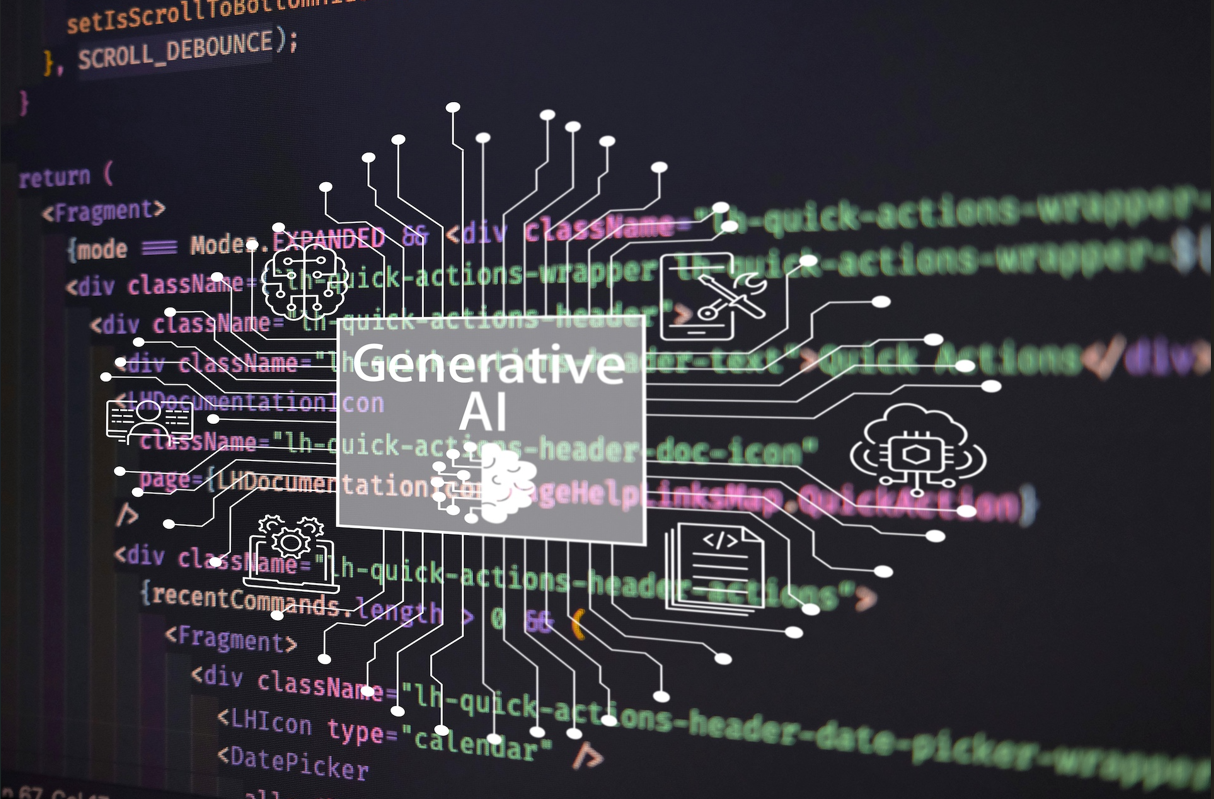知っておきたい!中小企業の契約書業務に生成AIを活用する方法
- 2025/11/1
- 診断士の視点

中小企業診断士・行政書士 箱山 玲
近年、ChatGPTなどの生成AIの進化によって、企業の契約書業務にも、AIを取り入れる動きが広がっています。
数年前までは、AIによる契約書業務といえば、大企業の法務部が専用のサービスでチェックなどを行うものでした。しかし、2024年頃からは、中小企業や個人事業でも、ChatGPTなどの汎用AIツールを利用して契約書をチェックあるいは作成するケースが増えています。
筆者は、前職で企業の法務担当者として契約書業務を日常的に行い、現在は行政書士として中小企業の契約書作成をサポートしています。
これらの経験を踏まえ、今回は中小企業の契約書業務における生成AI活用法と、注意点をご説明します。
なお、本記事の内容は2025年10月時点のものです。今後のAIの進化により状況が変化する可能性があります。
1.そもそも契約書業務では何をしているの?
生成AIの活用を考える前提として、企業における契約書業務を整理しておきましょう。
契約書業務を大まかに整理すると、①契約書を作成する、あるいは取引先から提示された契約書をチェックする、②押印または電子署名により契約を締結する、③締結済みの契約書を保管する――の3つです。
このうち、AI活用に関連するのは、①契約書の作成・チェックです。
契約書を作成・チェックするとき、たとえば15~30条程度で構成される一般的な取引契約書では、前半と後半に分けて検討します。契約書の前半と後半では、書かれている内容が異なるからです。
契約書の前半部分には、契約の目的、納期、価格などの「ビジネス条項」が書かれています。交渉結果である具体的な取引条件ですので、経営者や営業担当者がその内容をよく理解しており、逆に法務担当者や外部専門家は詳細を把握していません。したがって、経営者や営業担当者が方針を決め、法務担当者や外部専門家が法律文書の形に仕上げることになります。
一方で、後半部分には、損害賠償、解除、秘密保持などの「法的条項」が書かれています。専門的な内容ですので、法務担当者や外部専門家がその内容をよく理解しており、逆に経営者や営業担当者は専門外であることが多いです。したがって、経営者や営業担当者は、法務担当者や外部専門家に説明を求め、選択肢を提示してもらったうえで、内容を最終決定することになります。
ポイントは、契約書業務とは法務担当者や外部専門家にすべて任せてしまうものではなく、経営者や営業担当者の関与、判断が欠かせないということです。
2.契約書業務に生成AIを活用する方法
(1)生成AIにすべて任せることはできない
では、生成AIは契約書業務に活用できるのでしょうか。
結論から言えば、生成AIにすべて任せることはできないが、補助ツールとしては非常に有効です。
まず、前半のビジネス条項は、これから始める取引の内容です。AIが知りうる情報ではありませんので、生成AIから適切な回答が出てくるとは言えません。
一方、後半の法的条項は、定型的な条文(ひな形)が存在しており、AIが扱いやすい領域です。しかし、AIの回答が自社に有利か不利かは、人間が判断しなければなりません。
いずれにしても、生成AIに契約書業務を丸投げできない、ということになります。
しかし、契約書はひな形のデータが膨大に存在していること、法律文書として論理的に書かれていることから、言語処理の技術である生成AIと相性がよいのも確かです。
そこで、人間の判断を支援する補助ツールとして生成AIを活用するのが有効です。
(2)補助ツールとしての活用法
では、補助ツールとしてどのように活用できるでしょうか。活用法を3つご紹介します。
①リスクの洗い出し
契約書を生成AIに読み込ませ、「不利な条件やあいまいな表現を指摘して」と指示すると、一定の精度でリスクを抽出してくれます。たとえば「損害賠償の上限が定められていません」「解除条件が一方的です」といった回答が得られます。
AIの指摘をそのまま採用できるとは限りませんが、「どこに注意を向けるべきか」の目安をつかむには有効です。特に、後半の法的条項のチェックに相性が良いでしょう。
②合意事項との差異チェック
合意内容が契約書に正しく反映されているかを確認するのは、意外と手間のかかる作業です。
そこで、交渉時の提案書やメール、稟議書などを生成AIに読み込ませ、「この内容が契約書に反映されていますか」と指示することで、漏れや齟齬を発見できます。「支払期日が合意と異なります」「成果物の範囲が明記されていません」といった回答を得られれば、人間による確認作業を大幅に効率化できます。
この方法は、前半のビジネス条項のチェックに特に有効です。
③内容の理解や社内共有
契約書は専門用語が多く、慣れない人には読みづらいものです。
そんなときは、生成AIに「この契約書を新人にもわかるように説明して」と指示すると、やさしい表現で要約してくれます。社内で内容を共有したいときや、短時間で要点をつかみたいときに便利です。
3.契約書業務で生成AIを活用する際の注意点
契約書はビジネス上の繊細な情報が含まれていますので、契約書業務で生成AIを活用する際は「安全に使うこと」が最優先です。次の3つのポイントを押さえておきましょう。
①機密情報を入力しない
生成AIツールの多くは、入力内容が外部サーバーに保存され、学習データとして利用されます。取引先名、金額、住所などの機密情報は伏せるか、入力しても学習されない契約プランで利用してください。社内で生成AI利用のルールがある場合は、それに従わなければなりません。
②専門家を併用する
生成AIには、事実と異なる情報をあたかも正しいかのように生成してしまう現象(ハルシネーション)があります。出力結果は鵜呑みにせず、不明点や疑問点は弁護士などの専門家に相談しましょう。
トラブルが起きたとき、契約書の条項の解釈次第で不利な立場になることがあります。事業への影響の大きさを考えると、たとえばSNS投稿やWebライティングに生成AIを利用するときよりも、慎重になる必要があります。
③AIの回答を一次判断にとどめる
AIの出力結果は、あくまで一次的な判断材料です。「この条項は見直した方がいいかもしれない」と気づけるだけでも十分な価値があります。
AIの回答を踏まえて最終的な判断は必ず人間が行う――これが、AI時代の契約書業務の基本姿勢です。

4.まとめ
生成AIは、契約書業務を一変させる可能性を秘めています。しかし、AIは契約に関する「判断」や「責任」を代わりに担ってくれるわけではありません。
契約書業務では、「人間の思考を補助し、作業を効率化する」というAIの特徴を活かしつつ、専門家の力も上手に組み合わせて、人間が最終判断することが大切です。